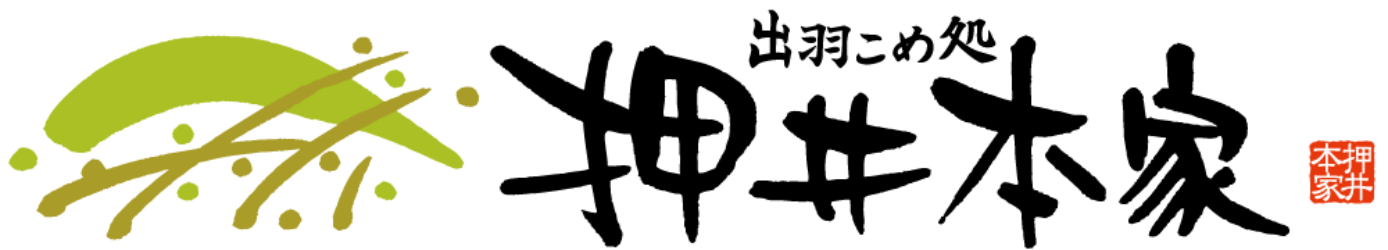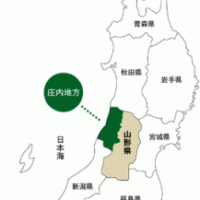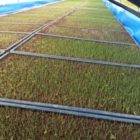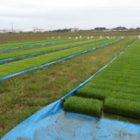5年生の社会科の授業! 山形県庄内地方の米づくりの様子を学んでいく中で、新たな疑問が生じ、手紙を書きたいという気持ちが芽生えたといいます。鶴岡市教育委員会宛に送られてきた手紙を、その場に居合わせた私の幼馴染でもあるN先生がわざわざ持って来てくれました。そこには、担任の先生と4人の子供達の手紙が入っていました。以下、子供達の質問にお応えします。
【SHさんからの質問にお応えします!】
① 米づくりをしている途中に休憩はするのですか?
回答:1日の仕事として考えると、朝食・昼食の時間の他に、午前中1回、午後2回の休憩時間があります。
○ 午前5:00~7:00 朝仕事(忙しいとき) 午前7:00~8:00 朝食
○ 8:00~10:00 仕事 10:00~10:15 休憩
○ 10:15~午後12:00 仕事 午後12:00~1:00 昼食
○ 午後1:00~3:00 仕事 3:00~3:15 休憩
○ 3:15~5:00 仕事 5:00~5:15 休憩
○ 5:15~6:00 仕事(忙しいとき)
※ 米づくりは自然の中で行われるので、天気予報を見ての仕事になります。

★ 農道でのいっぷく!
② 米づくりは大変ですか?
回答: 大変です。
「米」という字は、「八十八」と書きます。種まきの準備をして種をまいて白いお米(白米)になるまで、八十八の手間がかかると言われています。実際はもっとかかっていると思いますが。その作業を一つ一つ丁寧に行っていかなければなりません。
「米」ができるあがるまでは、「稲」という作物を育てなければいけません。「稲」の「実」が「米」になります。種籾をまくと芽を出します。この芽はどんどん葉っぱを出して成長し大きくなり、やがて実をつけます。成長するということは、生きているということです。稲が何の心配もなく生きれるように、その環境をつくってやることが稲を育てるということです。例えば、稲がのどが乾いて水を欲しがっているとき、稲は水のあるところに移動してその身を潤おすことはできません。人間が稲が水を欲しがっていることを察して、水をかけてやらなければなりません。一例ですが、これが稲を育てるということであり、人間が稲が水を欲しがっていることに気づかなければなりません。それには、観察力が大切になります。
朝、昼、晩と稲の状態を観察します。稲が何を欲しがっているのか、何をしてもらいたいのか、稲の声を聞きます。(よく観察する)そして、稲が良い状態になるように手を貸してあげます。人間が中心ではなく、稲が中心になります。これは大変です。

★ 田んぼに水を入れています。 朝5時止水直前の写真! 前日の夕方5時に入水!
生育初期の水掛けは、午後4時位から翌日午前8時位までの間に行います。日中に掛けると、圃場の長さが100mあるので、頭(かしら:水を入れるところ)と尻(しり:一番奥、排水するところ)の温度差で生育に差がつきます。頭の生育が遅れ(温度が低い)、尻の生育が早くなります。(到達するまで温度が上がるため)。圃場隅々の稲の生育を揃えることが増収の基本なのです。
③ 一人で米づくりをしているのですか?
回答: 私のうちの農業を中心とする仕事は、株式会社という会社形態になっており、私と家内、父、母の他に、常勤で来てくれる従業員が1人、忙しいときだけ来てくれる臨時従業員が5人ほどいて、仕事の量に応じて働いていただいております。
米づくりに関する仕事は、1. 米を生産する仕事、2. 米を販売する仕事、3. 経理等事務の仕事に大きく分けられます。
6.4haの水田で 1. 米を生産する仕事 常時2人(私と従業員)
春作業(種まき・田植えなど)で、全員の10人
秋作業(稲刈り・乾燥調製など)で、3人です。
2. 米を販売する仕事 3人
3. 経理等事務の仕事 2人
稲づくりは、いくら小さな面積でも1人ではできないと思います。最低でも2人は関わらないとできません。今は機械化が進んでいるからこそこれですんでいますが、昔は手作業がほとんどで、牛や馬を使ったとしてもとてつもない人の手がかかっていました。また今は、必要最小限の除草剤を使用している農家がほとんどですが、昔は手で雑草を取っていました。これもたいへんな作業なのです。
昔と比べて作業は大分楽になってはいますが、やはり「八十八」の手間がかかりますので、スタッフ一同協力して仕事をしております。
★ 写真中央:地元中学校の農業(田植え)体験学習! 田植え機に苗を積み込みます。
★ 写真右:籾摺り作業! 籾摺り機で籾殻をとって玄米にして、30kg入りの丈夫な紙袋に入れます。
【STさんからの質問にお応えします!】
④ 1年間の米の売上げはいくらぐらいですか?
回答: 目標ということでお応えいたします。自社生産分(6.4ha)を全て白米で販売することを目指しており、1,100万円ぐらいになります。(あくまで目標です。)
現在の米の価格は、農家の手取り価格で昭和48年前後の価格水準になっております。原因は、米の消費が落ちており、消費量を上回る生産量になっていて、米が余っていることによります。それにしても、昭和48年前後の価格水準では利益が出ません。私のうちでは、精米をして白米で消費者に直接販売することによって利益を生み出そうとしております。しかしながら、これだけでは会社は成り立たないので、仲間の農家から米を仕入れて販売したり、ハウスで野菜の苗を作って販売したり、干し柿をつくったり、もちをつくって販売したりしています。
これからの農業は、農産物をつくるだけでなく、加工したりして付加価値を高め、自ら販売していく必要があるのです。
★ 上段右:弊社で栽培したもち米(品種:でわのもち)を地元加工業者に委託し「まるもち」に加工!
★ 下段左:庄内柿を仕入れ、干し柿に加工!
★ 下段中央:弊社ハウスでなすの苗を生産、地元で販売!
⑤ 米づくりをして、うれしい時はどんな時ですか?
回答: 「米」という字は、「八十八」と書きます。種まきの準備をして種をまいて白いお米(白米)になるまで、八十八の手間がかかると言われていることをSHさんの質問でもお応えしましたが、春から一生懸命育てた稲が思うように立派に育ち、秋においしいお米がたくさん収穫された時、本当に涙が出るほどうれしいです。
稲は自然のなかで栽培されますので、天気の具合などでなかなかうまく管理ができないことのほうが多いのです。例えば、天気がいいと思って肥料をいっぱい与えたのに、予想に反して雨が降り続き、軟弱に育ち病気になってしまったりしたときなど・・・。(天気のいいとき稲は肥料をいっぱい欲しがり、曇りや雨の時はそんなに必要としません。)今度は病気が広がらないように対処します。こんなことの繰り返しが多く、なかなか自分が思い描く稲の姿になってくれません。そして収穫の秋を迎えます。手をかけた分だけ喜びも大きいのです。
★ 中段左:稲の種を播き終った苗箱をホロハウスに並べます。 保温のためビニールをかけます。
★ 中段中央:田植え! 中段右:田植え後7日!
★ 下段左:コンバインによる稲刈り!
★ 下段中央:「人と環境にやさしい農業実践圃場」標示! 稲は全て特別栽培米!
★ 下段右:精米した白米! 透明度で味がわかります! この輝きに感動!
⑥ どうして米づくりをしたいと思ったのですか?
回答:私のうちは代々米づくりをしていて、水田を荒らすことができなかったということがあり、米づくりを1年また1年と繰り返すうちに、米づくりが大好きになったというのが理由です。
一粒の米(種籾)から約350粒の米が収穫される(350倍になる)のが米づくりの魅力で、比較的毎年安定した収穫量が望めます。これが米が日本の主食になった理由でもあるのですが・・・。また、仕事は大変ですが、自分が努力した分だけおいしくなったり増収したりするので、いつの間にかそんな米づくりのとりこになってしまったのでしょうね。
★ 上段中央:田植え後20日 上段右:田植え後25日
★ 下段左・右:稲刈り直前、田植え後4ヶ月! 鳥海山をバックに!
【KYさんからの質問にお応えします!】
⑦ 1年間でどのぐらい収穫していますか?
回答:60kg単位で1俵(今は玄米30kg入りが1単位)といいますが、10a(100m×10m)当たり9.5俵(570kg)の収穫量があるので、6.4haでは・・・64×9.5俵=608俵(36,480kg)となります。
化学肥料が出てきてから、米はたくさんとれるようになりました。
★ 左2枚目:コンバインによる稲刈り、コンバインからトラックに籾排出中!
★ 左3枚目・右:低温倉庫に保管中の米! 1パレットに7袋×6段=42袋 × 4パレット積み!
⑧ 米づくりをしていて、いやなことはありますか?
回答:あります。体調が悪い時に作業をしなければならない時です。
稲は生きていますから、どうしてもその時期にやらなければいけない作業があります。例えば、種まきや田植えです。適期を逃してしまうと成長しすぎて作業がやりづらくなります。その時は、体調が悪くても無理をして作業をしなければなりません。私も人間ですから、体調が悪い時の作業はいやになります。
⑨ 米づくりをしていて、うれしいときはどんな時ですか?
回答:STさんの ⑤ の回答をみてください。
★ 上段右:コンバインによる稲刈り!
★ 下段左:コンバインによる稲刈り、コンバインからトラックに籾排出中!
★ 下段右:稲穂と真っ白い塩おむすび!
【KUさんからの質問にお応えします!】
⑩ 農業を始めたきっかけは何ですか?
回答:STさんの ⑥ の回答と少し重複しますが、私のうちが代々米づくり農家で、小さい時から農業のある環境の中で育ってきて、それをするのがごく自然の流れでした。特別なきっかけというものはありませんが、自然の中で働ける農業が好きだからなのでしょうね。
★ 虹と稲穂!
★ 朝日と温海かぶ!(山形県庄内地方に伝わる伝統野菜:お正月用の漬物になります)
⑪ 農作業で、一番たいへんな作業は何ですか?
回答:力作業です。春作業では、稲の種を播いた育苗箱をホロハウスに並べる作業や、田植えをするために大事に育てた苗を苗箱ごと田んぼに運ぶ作業などがあります。水を含んだ苗箱を持ったり、腰を曲げて並べたりしなければならないので大変です。ちなみに10a当たり25箱~30箱苗を準備するので、6.4haで、64×27箱=1,728箱 になります。とても1人ではできないので、若い人達全員で行います。
秋作業では、玄米になった米を30kg入りの紙袋に入れて出荷したり保存したりするのですが、これを持ち上げてパレットに30袋または42袋積み上げる作業があり、これもまた力作業で、手や腰が痛くなります。6.4haでは・・・64×9.5俵=608俵で、30kg入りなので、608×2=1,216袋 になります。
★ 中段左:田植え作業、苗を農道に運び並べます。
★ 中段右:地元中学校の農業(田植え)体験学習! 田植え機に苗を積み込みます。
★ 下段左:籾摺り作業! 籾摺り機で籾殻をとって玄米にして、30kg入りの丈夫な紙袋に入れます。
★ 下段右:低温倉庫に保管中の米! 1パレットに7袋×6段=42袋 × 4パレット積み!
⑫ 農業をしている中で、はげみになる言葉は何ですか?
回答:何と言っても、消費者の皆さんの「おいしい」という言葉が涙が出るほどうれしく励みになります。「よし、また頑張ってつくろう。」という気になります。また、もしお客様が満足いく味にならなかったとしても、足りないところを指摘してくれることがこれまた励みになります。「今度こそはここを改善してつくろう。」という気になります。
⑬ 農業をやめたいと思ったことはありますか?
回答:あります。一生懸命やったのにうまく育たなかった時です。農業でもっとも気を使う時期で、うまくいかなかった時のショックが一番大きいのが、「育苗」と言って苗を育てる時期です。発芽がしなかったり、苗が何らかの原因で枯れてしまったりすると、泣きたくなるほどショックをうけ、「もうやめたい」と一瞬思ったりします。しかし、「もう一度一からやり直そう。」と思いとどまり、何が悪かったのかよく分析をしてやり直します。
苗がうまくできないということは、植えるものがないということで、収入が全くゼロということになり、それはそれはショックが大きいのです。
ただ、この一大事を乗り越えたときの達成感は言葉では言い表せません。そして、技術的にも精神的にもひとまわり大きくなっている自分に気づきます。「何事も成功するまでやる。あきらめたときが失敗。」ということを学びます。全てに通じることだと思います。
「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」と言ったのは、江戸時代の米沢藩主(山形県)の上杉鷹山(うえすぎようざん)という人ですが、人が何かを成し遂げようとする意思を持って行動すれば、何事も達成できるということで、何も行動を起こさなければ良い結果には結びつかず、結果が得られないのは、成し遂げる意思を持って行動をしないからということなのです。
みなさん、何事もあきらめないで頑張ってくださいね!
★ 上段左2枚目:なんとか発芽してきました。 播種後7日!
★ 上段左3枚目:大分成長しました。「大丈夫」、ホッとします。 播種後14日!
★ 中段左・中央:田植え直前の苗! 播種後25日!
★ 中段右:田植え直前の苗! 苗箱の下に伸びた根、根張りで作物の健康状態をみます。Good!
★ 下段:苗の管理は朝が勝負! 「元気に、丈夫に育ってくれ」と毎日祈ります。